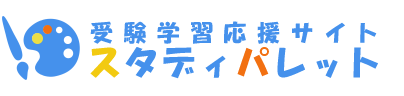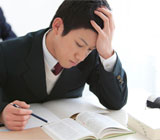「筆者の心情を答えなさい」問題に意味はあるの?実は論理的だった長文読解

「小説の解釈なんて人それぞれなんだから、対策なんてできっこないよ。」
と思っていませんか。
あるいは「私は小説にあんまり感情移入できないから問題が解けないんだよね。」
と思いこんでいませんか。
実は小説問題の解き方はとても論理的ですし、感情移入しないほうがきちんと解けるのです!
小説問題に対する正しい取り組み方を身につけましょう!
感情移入は絶対にタブー!
まずよくある間違いとしては「感情移入」があります。
出題された主人公に、似たような経験など自分との共通点を見つけてしまうと感情移入し、主人公の状況が自分の思いこみによって上書きされてしまいます。
このパターンに陥ってしまうと、大問すべて落としてしまうことも珍しくありません。
個人的に小説を楽しむときは大いに感情移入した方が楽しめるかもしれませんが、「入試問題」を解くときには必ず頭をクリアにして「思いこみ」が発生しないようにしましょう。
こういう筆者も普段はセンター国語9割取れるのですが、センター過去問を解いているときに感動の余りに涙して自信満々に問題を解いた結果全部はずして大問丸ごと落としたこともあったくらいです。
近年のセンター国語は感情移入できないものが多い
そもそも感情移入がタブーといっても、近年のセンター小説の問題は「最後に登場人物が思わぬ行動をして、その真意を問う」問題が頻出になっています。
しかも、その行動が一般生活からは想像できない行動なだけに、感情移入は解けない問題になっているのです。
このことからもセンター試験などの入試の小説問題は「普通に小説を楽しむだけ」では解けないギミックになっていることがうかがえます。
また通常の小説では、たとえば恋愛経験がないと読みとれない恋愛描写などもありますが、入試という特性上このような問題はまず出ないと思って良いです。
意外と役に立つ「空気を読む」スキル
現代文全体に役立つのが、案外「空気を読む」スキルだったりします。
つまり、「ささいな描写などを見逃さず読みとり」「出題者の期待する答えを見つける」能力です。
小説問題は、あなたの解釈は誰もきいていません。
小説問題で正解になるのは「みんなはどう解釈するか」なのです。
そして「みんなの解釈」の理由づけとして「論理的に導き出せる正解」でなければ問題として成立しないのです。
「空気を読む」スキルにたけている人は「みんなはどう解釈するか」を無意識にわかってしまいます。
逆に考えると現代文演習は「同じ現象を他人がどう捉えるかわかるようになる」訓練とも考えられるのかな、と個人的には解釈しています。
小説問題を解く流れ
小説において「論理を追う」とはどういうことか。
端的にいうとこれは「登場人物の行動を追う」ことです。
数字で例えると、文章中から必要な数字を取り出して、
2→4→○→8
の○の部分が何か考えること。
これが小説を解く際の流れだと思ってください。
登場人物の行動に線を引いて整理し、この行動はなぜなのか?次はどうするのか?を埋めていくのです。
正解は「みんなの解釈」なのですから、かならず文章中にヒントがあります。
ヒントはたくさんある
登場人物の行動以外にも、理解するヒントはたくさんあります。
まず一番重要なのが、本文に入る前の短い状況説明部分。
これは絶対に熟読してください。
小説の一部(出題された部分)を理解するために、その前の膨大な文字数をそこに集約しているのです。
つまり冒頭には、最低限の必要な情報しかかかれていません。
そもそもなぜそのシーンに至ったのか、登場人物は何者なのかなど、しっかり把握しましょう。
次に、意外とヒントになるのが「登場人物の名前」です。
たいていの小説の登場人物は、人物像と名前が一致するように作ります。
たとえば「マリンちゃん」という名前の、現代社会のくたびれた独身OLはめったに出ません。
おそらくかわいい女の子や、周囲の人のマスコット的な存在の女性でしょう。
このように本文中や、本文以外にもさまざまなヒントがちりばめられています。
「受験生全員が解く入試問題」である以上、かならず与えられた情報で解けるようになっているので、あきらめずにヒントを探しましょう。
センター試験では一つの解釈違いで全部の問題を落とすようになっている
一つだけ注意をしておくと、センター試験の問題は
①解釈1
②解釈2(これが正解)
③解釈3
④解釈4
というように解釈できるようになっており、どれか一つの解釈を選ぶと小問の選択がすべて決まるようになっています。
つまり、
①本文を読み切って、「解釈3だ!」と思う。
②すべての問題に解釈3でつじつまのあう選択肢を選ぶ
③すべての問題を落とす
危険性があるのです。
なので、もしも自分の解釈で解答が決まっても油断しないようにしてください。
まとめ
小説問題では「感情移入」は必要ありません。
入試問題である以上、「あなたの解釈」ではなく論理的に導きだされる「みんなの解釈」を正解にせざるを得ないからです。
つまり本文中のヒントを組み上げるとかならず一つの答えにたどり着くようになっているのです。
なので「作者の気持ちなんか知らないよ」と投げ出すのではなく、現代文もしっかり復習しながら取り組んでみてくださいね。
執筆者:てんもんたまご
天文学者を夢見て浪人の末に物理学科へ入学。
卒業後は、理系としての知識や実験教室でのアルバイト経験を活かしてライターとして活躍中。
大好物は、紅茶とあんみつ。
_180118.jpg)
_180118.jpg)
関連記事
人気記事一覧
- 受験勉強でダイエット...36,498ビュー
- 力み過ぎ注意!受験勉...11,867ビュー
- 受験勉強と筋トレの意...5,299ビュー
- 一日10時間勉強の神...4,237ビュー
- 【最悪の勉強姿勢】寝...4,200ビュー
-
四谷学院 大学受験予備校
-
四谷学院 大学受験予備校